
「ワクチンNavi」 は渡航前に確認しておきたい感染症の情報や、旅行・渡航に役立つ豆知識など様々な情報を発信しております。
公開日:2025.10.22更新日:2025.10.22
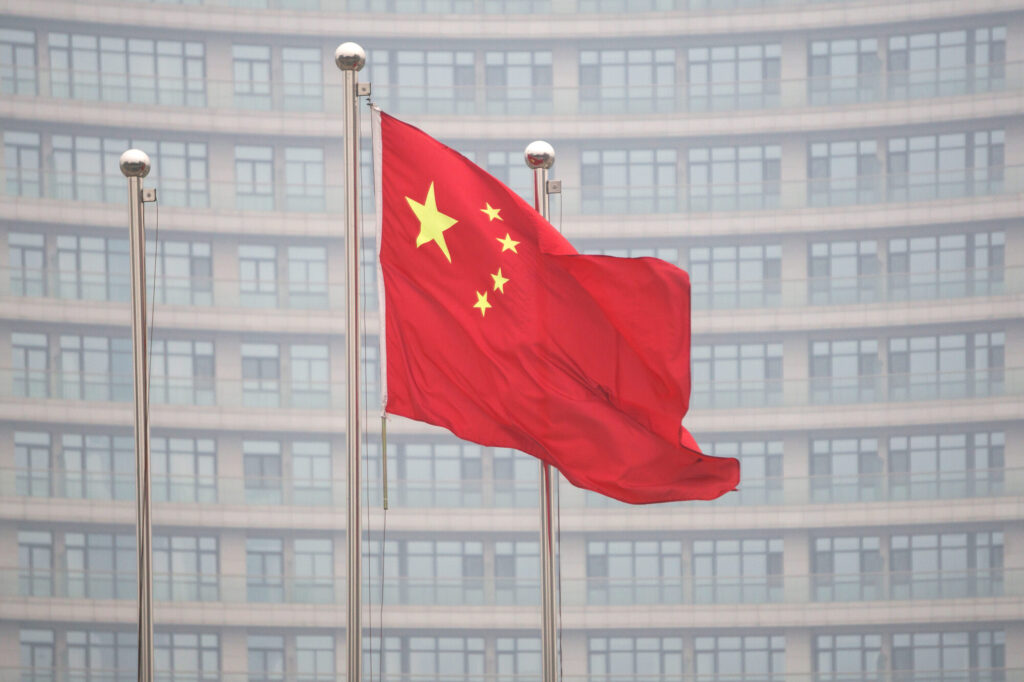
中国では経済発展とともに医療水準が向上していますが、日本とは制度や支払い方法が大きく異なります。公立病院は安価な一方で言語の壁があり、国際クリニックは高額になりがちです。旅行者や駐在員が安心して医療を受けるには、制度の仕組みと費用の目安を理解し、保険や予防接種などの準備を整えておくことが大切です。
中国の医療制度は、「社会医療保険制度」を基盤として整備されています。政府統計によれば、基本医療保険の加入率は約95%前後に達しており、国民の大多数がなんらかの公的医療保険に加入しています。
ただし、日本のように全国一律の保障ではなく、地域や職業によって給付内容や負担割合が大きく異なるのが特徴です。主な制度は以下の3つです。
| 制度名 | 対象 | 特徴 |
| 都市従業員基本医療保険(UEBMI) | 会社員・公務員など | 企業と従業員が保険料を負担。給付率がもっとも高く、保障内容も比較的充実。 |
| 都市住民基本医療保険(URBMI) | 自営業者・無職の都市住民 | 任意加入制。給付率は従業員保険より低く、自己負担割合が高い。 |
| 新農合(NRCMS:新型農村合作医療制度) | 農村部住民 | 国・地方自治体の補助で運営。医療水準・給付額に地域差が大きい。 |
この3制度は長年並行して運用されてきましたが、現在は都市住民保険(URBMI)と新農合(NRCMS)の統合が進められ、全国的に一体化を目指す改革が進められています。
一方で、給付率や診療の自己負担割合は地域や医療機関のランクによって異なり、同じ治療でも都市と地方で負担額が大きく変わることがあります。
また、保険加入地以外で受診した場合には給付対象外となる場合があり、自己負担となることもあります。出張や転居などで別地域の病院を利用する場合は、事前に「異地就医(跨省就医)」の登録手続きが必要です。

中国では、病院が「一級・二級・三級」の等級に分類され、それぞれが甲・乙・丙クラスに細分化されています。この制度は「医院等級制度」と呼ばれ、病院の規模や医療水準、診療範囲を定める全国的な基準です。
最高ランクの「三級甲等医院(通称・三甲医院)」は、省や市レベルの大規模総合病院で、高度な専門診療・教育・研究機能を担っています。北京・上海・広州などの大都市に集中しており、医療レベルが高く、外国人駐在員や旅行者も多く利用しています。
| 病院ランク | 概要 |
| 一級医院 | 地域の診療所や医療機関。日常的な外来診療や慢性疾患の管理を担当。 |
| 二級医院 | 地方都市や区レベルの中規模病院。一般的な入院設備を備え、地域医療の中心的役割を担う。 |
| 三級医院 | 省・市クラスの大規模総合病院。専門医や最新医療機器を備え、複雑・重症疾患にも対応。 |
多くの医療機関では、診療や検査、入院の前に保証金(デポジット)の支払いを求められることがあります。特に外国人診療部門や私立病院で多く見られ、支払った保証金は退院時に精算されます。
一方で、すべての公立病院が「前払い制」と定めているわけではなく、支払い方法や金額は地域・病院ごとに異なります。
また、中国では救急車の利用が有料となる場合が多く、料金は走行距離や使用機材、都市によって異なります。
中国の医療費は、病院の等級(三級甲等など)や都市によって大きく差があります。特に、外国人が利用しやすい「国際部門」や私立クリニックは、公立病院に比べて高額になる傾向があります。
公立病院では、診療費や検査費は比較的安価です。外国人が受診する場合でも、標準的な診察であれば以下のようなケースが見られます。
| 項目 | 費用の目安(人民元) | 日本円換算 |
| 初診料 | 20~50元 | 約400~1,000円 |
| 検査料(血液検査など) | 100~300元 | 約2,000~6,000円 |
| 入院費(一般病棟・1日あたり) | 50~200元 | 約1,000~4,000円 |
これらは主に地方都市や標準病棟での目安であり、都市部や高等級病院(三甲医院など)ではより高額になる場合があります。なお、病院によっては薬剤費や検査費が別途加算されることもあります。
外国人駐在員や短期滞在者が利用しやすい「国際クリニック」や「私立病院」は、医師やスタッフが英語・日本語に対応しており、快適な診療環境を備えていますが、その分費用は高額です。
| 項目 | 費用の目安(人民元) | 日本円換算 |
| 初診料(内科・一般診療) | 500~3,000元 | 約1万~6万円 |
| MRI検査 | 3,000~10,000元 | 約6万~20万円 |
| 手術(整形・消化器など) | 数万~十数万元 | 約数十万~数百万円 |
北京や上海などの外資系医療機関では、風邪や胃腸炎といった軽症でも診察料が1,000元(約2万円)前後となることがあります。また、入院・手術を伴う場合は、日本より高額になるケースも珍しくありません。
外国人旅行者や駐在員が中国で医療を受ける場合、次のような注意点があります。
1.診療は前払い制(デポジット制):治療や検査を受ける前に保証金を支払う必要があります。支払わないと治療を受けられないケースもあります。
2.保険のキャッシュレス対応が重要:多くの公立病院では海外旅行保険を直接適用できず、患者が一時的に全額を支払い、後から保険請求する方式です。国際クリニックや外資系病院では、保険会社との直接精算(キャッシュレス)に対応しているところもあります。
3.英語・日本語対応の医療機関を選ぶ:中国語のみの病院では、診療内容や費用説明を理解するのが難しい場合があります。主要都市には、通訳や日本人医師が常勤するクリニックもあります。
4.治療前の見積もりを必ず確認:検査・薬剤・入院費が細かく分かれて請求されるため、事前に費用の目安を把握しておくことが大切です。

中国では、入院や手術を伴う治療になると、医療費が非常に高額になることがあります。都市部の高級病院や国際部門では、医療機器やスタッフの水準が高い一方で、治療費も公立病院より大幅に高く設定されています。
実際の事例では、脳出血などの重症治療で200万円前後、骨折手術と長期入院で1,000万円近くかかった例も報告されています。一方、軽症の入院(数日間)でも10万円前後となることがあり、日本と比べても決して安くはありません。
特に外国人が入院や手術を受ける場合は、事前に保証金(デポジット)の支払いを求められることが多く、現金またはクレジットカードで高額の支払いが必要になる場合があります。さらに、医療搬送や家族の渡航費が加わると、総額が数百万円に達することもあります。
海外での予期せぬ病気や事故に備えるためには、入院・手術・搬送費を十分に補償できる海外旅行保険への加入が不可欠です。
中国で安心して医療を受けるためには、海外旅行保険や駐在員向け医療保険への加入が不可欠です。現地の医療費は公立・私立の差が大きく、国際病院を利用する場合は日本国内の数倍の費用になることもあります。
そのため、保険を選ぶ際は以下の3点を重視しましょう。
現金での前払いを求められる医療機関が多いため、保険会社と提携している「キャッシュレス診療対応」の病院を利用できるプランを選ぶと安心です。
現地での支払い手続きが不要になり、通訳や医療手配のサポートを受けられる場合もあります。
重症時に日本への緊急搬送が必要になると、チャーター便で数百万円規模の費用が発生することがあります。
搬送費や家族の渡航費も補償対象に含まれているかを、必ず確認しましょう。
現地での治療費は入院1日あたり数万円、手術では数十万~数百万円かかるケースもあります。
「治療・救援費用」の上限が1,000万円以上のプランであれば、ほとんどのケースに対応できます。
中国では医療制度は整備されていますが、医療費の支払いは原則として前払い制であり、外国人は保険が適用されないケースが多いのが実情です。
公立病院は費用を抑えられる一方で言語の壁があり、国際クリニックは高額になりやすい傾向があります。
万一の病気や事故に備えて、キャッシュレス対応の海外旅行保険に加入し、感染症予防ワクチンの接種も出発前に済ませておきましょう。
ワクチンナビでは、渡航先や目的に合わせて最寄りのトラベルクリニックを検索できます。医療費やワクチンの準備を早めに確認し、安心して中国滞在をスタートしましょう。
Related article